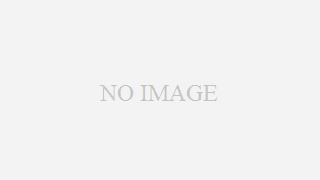 中長距離走
中長距離走 中長距離走で記録を伸ばすヒント集:為末大さんのYouTubeから考える
競技のやめ時 ー よりも深い話 日本のスポーツの特徴に「本気でやるか」「やらないか」の二択、というものがある。オランダでは、8~9割は、何かになろうともしてないし、上手くなろうとも思っていない。 なぜトレーニングをしなくてはならないのか?い...
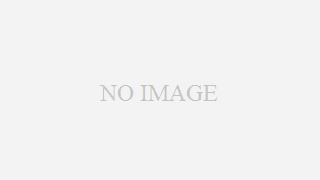 中長距離走
中長距離走 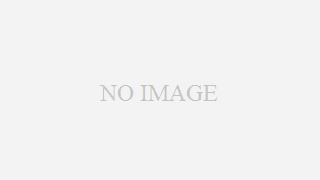 中長距離走
中長距離走 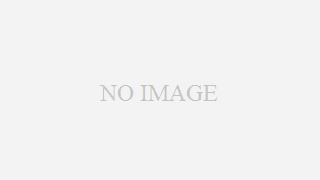 中長距離走
中長距離走 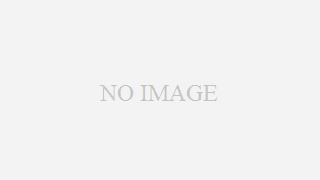 中長距離走
中長距離走 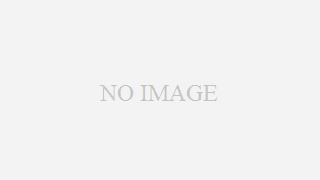 中長距離走
中長距離走 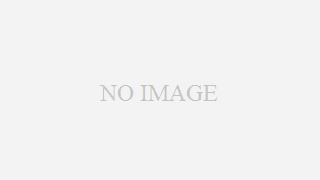 中長距離走
中長距離走 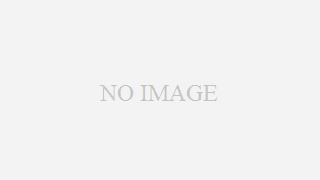 中長距離走
中長距離走 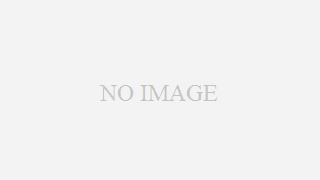 中長距離走
中長距離走 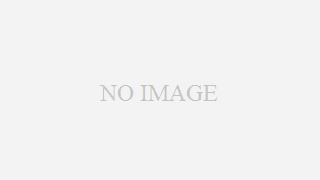 中長距離走
中長距離走 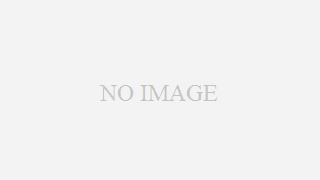 中長距離走
中長距離走